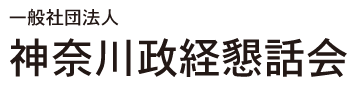「相模国と横浜」
| 開催日 | 2025年1月16日(木)午後2時00分~3時30分 |
| 会 場 | ロイヤルホールヨコハマ5階「リビエラ」 |
| 講 師 | 東京大学史料編纂所教授・歴史学者 本郷 和人 氏 |
歴史学者で東大史料編纂(へんさん)所教授の本郷和人氏が16日、横浜市中区のロイヤルホールヨコハマで講演(神奈川政経懇話会主催)し、神奈川県の元となった相模国(さがみのくに)と武士の結びつきなどについて解説した。
 「相模国と横浜」と題し、まず、相模国の国府(律令〈りつりょう〉制の地方行政府)について説明。「国分寺があった海老名から平塚、大磯に移転した」などとする三遷説に対し、発掘調査の成果から「最初から平塚にあり、後に大磯に移転したとする二遷説が有力化している」と紹介。その相模の鎌倉に源氏が本拠地を置き、以後、武士にとって相模は特別な国になったという。
「相模国と横浜」と題し、まず、相模国の国府(律令〈りつりょう〉制の地方行政府)について説明。「国分寺があった海老名から平塚、大磯に移転した」などとする三遷説に対し、発掘調査の成果から「最初から平塚にあり、後に大磯に移転したとする二遷説が有力化している」と紹介。その相模の鎌倉に源氏が本拠地を置き、以後、武士にとって相模は特別な国になったという。
「鎌倉に幕府を開いたのは、源氏のスーパースターである八幡太郎義家(源義家)の父・源頼義が相模守で、武の神である八幡様に信仰を持っていて、鎌倉に鶴岡八幡宮を造ったから」とした。当時、「国は1軍から4軍に分けられるが、関東では相模、武蔵、伊豆、駿河が1軍だった。特に北条氏は鎌倉時代を通じて武蔵、相模国を手放さず、相模は、北条氏の金城湯池(きんじょうとうち)だった」と続けた。
4カ国はいずれも富士山を見られる地域で、「武士の存在と霊峰富士は結びついていると思う」と主張。源頼朝が長男の頼家を後継者として披露した「富士の裾野の大巻狩り」をしたり、徳川家康が隠居先を富士山がよく見える駿府にしたのも同様という。相模について江戸幕府も、小田原藩(ほぼ10万石)を除き、天領(幕府領)とし、特別扱いしてきたとした。
ほんごう・かずと 1960年東京都生まれ。83年東京大学文学部卒。同大学・大学院で石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本中世史を学ぶ。史料編纂所で「大日本史料」第五編、鎌倉時代の編纂を担当。96年博士(文学)号取得。2012年から現職。同年のNHK大河ドラマ「平清盛」のほか、中世や近世を扱ったさまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。「日本史のツボ」(文春新書)、「承久の乱 日本史のターニングポイント」(同)、「世渡りの日本史 苛烈なビジネスシーンでこそ役立つ『生き残り』戦略」(KADOKAWA)、「『失敗』の日本史」(中公新書ラクレ)、「変わる日本史の通説と教科書」(宝島社新書)、「歴史をなぜ学ぶのか」(SB新書)「鎌倉殿と13人の合議制」(河出新書)など著書多数。